Before the sun goes down
「は、あっ」
「……っと」
ふいに襲った震えのくる快感に思わず身を竦ませると、ディーノは下半身をまさぐる手を止めて窺うようにヒバリの顔をのぞき込んできた。
後ろからさし込まれた中指はまだ浅い入り口に留まっていて、なかなか奥へと進んでいかない。衣服は下着まですべてはぎ取られ、腰を半端に浮かせて向かい合わせに跨るというとんでもない体勢なのも、さらにいたたまれなさを感じてしまう大きな要因だった。あと少しだとわかるのに最後の一線をどうしても超えられない。焦りと苛立たしさで体の奥のほうがじりじりする。
「……まだ、ダメか? きつい?」
そうじゃないと言う代わりに目を細めてにらみつけると、脳天気なイタリア男はあーそうか、もしかして、とひときわ顔を輝かせた。
「すげー顔がえろくなってきたもんな。そそる……」
バカなことを口走ったすぐあとになかで指先だけをあちこち動かして、じゃあこれは、気持ちいいかと訊いてくる。
「…ひっ、あ……」
下から強く押し込まれた反動で喉が鳴り、ヒバリはびくびくと体を震わせながら背を弓なりに反らせた。弱いところにまともに指が触れたのだ。ディーノには全部知られているから自分でポイントを外すなんてできなかった。互いの体のあいだに挟まれた自分のものがはしたなく揺れるのがわかる。さっきからひっきりなしにディーノの胸や腹を汚していることも。
「そうやって遊ばれるの……むかつく、ん……だけどっ」
「遊んでねーって。もっとえろい顔させたいだけだって」
抗議のつもりで言ったのだけれど、普段は絶対に見せないヒバリのせっぱ詰まった表情はディーノを喜ばせただけだった。
乱暴な言葉とていねいな愛撫は「飴と鞭」と同じバランスだ。
ディーノがヒバリをひらくことにバカみたいに慎重になるのは、身体のことはもちろん心のほうの準備をより大事にするからなのだが、過ぎるくらいに感じていることを百も承知でいながらわざわざ言葉にされると、恥ずかしいよりも先に腹が立つ。
「うわ、ここもすげー汗……きらきら光ってる」
くすくす笑いながら、首すじから肩──胸のすぐ上まで舌で触れてくる。
だめなわけがない、それなら最初から触れさせてもいない。
だからそこで遊んでないでさっさとすれば、早くほしいと怒鳴りつけてやれたら、どんなにか気が晴れるだろうに。
けれどもヒバリは荒い言葉を吐き出すことはせずに、はだけかけたディーノのシャツをつかんで目を瞑った。
ディーノの帰国の日が近づくとふたりはたいてい夕方というには早く、昼間というにはやや遅い中途半端な時間に抱き合うことが多かった。いま求めないと明日にはいない。現在が過ぎれば次という日はないからだ。
夜が明けたらディーノが日本を離れる今日も同じで、ヒバリが授業を終えるのを待って日差しがきついうちにホテルの部屋に入り、それからはほぼ一ヶ所──ほとんどの時間をベッドの上だけで過ごして、気づくとすでに夕方に近かった。
日が長くなる季節になると午後五時を過ぎてもうんざりするほどあかるく、部屋の中の隅々までをハッキリ見渡せる。窓を白く染める太陽は窓ガラスに吸い込まれて弾け、無彩色の絨毯の上に落ちるとそこに長い長い影を作った。白と黒だけで構成される光のアートだ。
ディーノは陽が高いうちにカーテンを引くのをどうしても嫌がるから、ヒバリの目にはディーノの髪や引き締まった胸板や、水に濡れたように光る指先までが見えている。つまりこちらの姿も相手にすべて見られているということだ。ヒバリは急に自分の貧弱な体型が気になった。今までにもっと隅々まで、もっととんでもない格好まで見られているのに、ディーノの目前に自分の裸をさらすことにはいつまで経っても慣れない。達したショックで頭の中がまっしろになって、ぼうっとしている顔を見られるのも苦手だった。
「ここ……あかくなってる」
ふわりと笑顔を見せて顔を傾け、ディーノがヒバリの胸の両側の突起を交互に口に含んだ。一度終わりを迎えたからだはこの程度の接触でも簡単に火が点く。ヒバリがすぐに反応したのがわかるとディーノは困ったように眉を寄せ、ぐっと伸び上がって今度は唇にゆっくりくちづけてきた。
「危ない顔してる。なんかこのまま溶けちまいそうだな。さっきも中が、すげえ熱かったし……」
「……っ」
ヒバリが思わず目を開けると、ディーノはヒバリの前髪を梳きながらにこにこというか、あからさまににやにやしながらヒバリの唇の上で小さな音を鳴らした。
すでに誤魔化せないくらいまで追い込まれたあとだ。ただ触れるだけ──表面をかすめるくらいでは物足りない。
「もっとディープなのがくると思った?」
でもそれを面と向かって言われたくはない。
「…………もう、あなたとは、しゃべらない……」
「うそ」
こういうコトをされるとヒバリが嫌がることも、投げつけられる辛辣な非難の台詞も全部わかっているくせに、ディーノはたまにこういう悪戯をしかけてはヒバリをわざと怒らせようとする。照れ隠しだとしても質が悪い。
「ごめんもう一回、今度はちゃんとするから……ホントに、あいしてる、恭弥」
囁き声の合間にまた唇が触れあった。何度も何度も、ついばむようなキスをくり返して唇を開かせ、舌をそおっと潜らせて、ディーノがヒバリの中に少しずつ自分の領域を拡げてゆく。
鍵を外してヒバリを求めてくるとき、ディーノはこういうていねいなキスを何度もくれる。
簡単には触れさせない部分を直に触れあわせて、離れるごとにわかるのだ。まるでスイッチを入れるみたいに、最奥から外に向かって暴かれてゆくのが。からだの奥のほうがうずくような誘惑。開け放たれた扉から今まで知らなかったあまい衝動が引き出され、自分が自分とはちがういきものになってゆくようだった。
「……っ、んっ」
むさぼるようだった唇が離れて顎や舌が楽になると、途端に口がさびしくなる。
ヒバリが目を開け、ディーノの視線が自分に注がれていることに満足して、もう一度こめかみが痛くなるくらいにぎゅっとつぶると、昼間の光が閉じた目蓋の裏に残った。
しろいような、きいろいような幾筋ものまばゆい光の束。
黄色じゃなくて金色なのかも。きっとそうだ。見えなくなる寸前に視界を掠めたディーノの髪の色が目に焼きついているのだ。
ディーノが定宿にしているとあるホテルの最上階の窓からは、青からわずかにグレイに傾いた空しか見えない。ディーノがヒバリの上を行ったり来たりするあいだに、ヒバリは何度も目を閉じたり開いたりして、遠くに広がる雲の流れに気を取られているふりをする。「オレとしてる時って恭弥はホントうわの空な」とからかい半分本気半分で責められるのだけれど、そうでもしないとヒバリがすぐにあふれそうになることをディーノは知らない。
最初からずっと絡ませている手を揺らして先を促すと、ディーノは意外そうにヒバリの顔をまじまじと見返してきた。
「ホントどうしたんだよ。今日の恭弥、変だぜ」
やわらかい声で苦笑混じりに、いつもこんなに素直だといいのにと笑う。
それには答えず、ヒバリはディーノの肩につかまって体を起こした。
部屋はまだじゅうぶんにあかるい、けれどもいつか日は沈んで今日は終わり、体と体がいやでも離されてゆき、次の朝にはディーノはいってしまう。
時間がないとか。
今日はこのあと家に送り返されてしまうだろうとか。
急かす理由を考え出したらそれこそいやになるほどたくさん思いつくのだけれど、真実の理由は実は違うところにある。残された時間は少ない。限られた時間の中でこの人とできるかぎり長く深くつながっていたかった。
「こら待て。ダメだって。ちょ、待て無茶っ……」
「待たない」
一度受け入れたあとだし、自分の身体のことは自分が一番よくわかっている。ためらう必要はなかった。
わざと見せつけるように片腕をディーノの首に巻きつけ、もう片方を自分のうしろに回す。最初は自分で、途中からは支えてもらいながら、ヒバリはゆっくりとディーノを飲み込んでいった。
胃が迫り上がるような圧迫感を感じたのはほんの一瞬だった。
「は、……ぁ」
思っていたよりもずっと楽に、先から半分ほどを収めて息をつく。向かい合って相手に体重を預けると身体が楽で、自分の好きなように動けるから快感も深い──はずが、少し動いただけですぐにわかってしまった。
「……これ、やだ」
「え? うわっ、わ、バカ、あぶねーって!」
考えるよりも体のほうが先に動いた。ヒバリが全体重をかけて思いきり首にしがみつくと、不意を衝かれたディーノは大きく前に体を傾かせた。慌ててマットレスに手をついて、自分よりもうんと華奢なひとの上に倒れ込むのだけはどうにかこらえる。
「は〜……危なかった……」
ヒバリの思いがけない大胆な行動は、いつもは余裕のあるひとをかなり驚かせたようだった。目をぱちくりさせて複雑な表情を浮かべている。
「なに?」
「なにっつーか、びっくりした……」
「だから、なに」
「や、……恭弥って乗っかるよりも上からされるほうが好きなのか。知らなかった……」
こんな場合なのに吹き出しそうになった。そんなことは一言も言っていないし、ヒバリが強引に体勢を入れ替えたほんとうの理由に、ディーノはまったく気がついていない。
「そうだよ。次はおぼえておいて」
ああ、わかったとディーノはうれしそうに言って、いったん抜いて同じ場所にあてがい、角度を変えてさらに深く押し入ってきた。
そのまま一気に貫かれるかと思っていたのに、ヒバリの期待に反してなかの浅いところであやすような動きをくり返している。初めから激しくしないのは自分よりもうんと負担の大きいヒバリを思ってのことだ。
「もっと、奥で……っ」
好きなように動いてほしい。そんなふうに我慢しないで。そんなことは言えない。ディーノは目を細めて軽く肯くだけだ。全然伝わっていないのだ。
「ん、……もう少し…ゆっくり、な」
ディーノは、照れたように鼻の頭をしわよせて、
「実はオレのほうがちょっと、やばい……」
そんなのうそだと思うけれども、今はこんなふうに甘いだけのやり方がよかった。
ディーノがヒバリの両足をゆっくり抱え上げた。
探るように、やがて二人ともがよくなる位置をうまく見つけると、ゆるやかだった律動が少しずつ速まっていく。暗くなり始めた意識の隙間を縫って、湿った水音とディーノの気配と声とが同時に耳にすべり込んできた。
高い音を鳴らして肌と肌とが打ちつけられる。寒さに震える時のようにヒバリが身体を揺らすと、それにつられて内側に留まるひとを刺激する。ディーノが初めてうめき声らしいものをもらした。
ぎりぎりまで引き抜く時の押し殺した吐息や、少し遅れて最後を迎えるときのディーノの声がヒバリはとても好きだ。他人にはとても聞かせられない、やらしい声だと思う。
「ディーノ、……ディー、ノ……」
突き上げられるリズムと同じ間隔で、ヒバリの口からも自然に声が漏れ出した。
交わりがもっとも深く、激しくなる時にヒバリがディーノの名を口にするのは、恥ずかしいほど乱れる声を抑えるためにすぎない。
「ディ、あぁっ…あっ……や、ぁ」
「うっわ、なんつーえろい声っ、それやばいって……」
自分のコトを棚に上げてディーノが笑う。
と同時に、なかを味わうようだったゆるい抽挿がいかせる時のそれに変わってゆく。こちらが煽ったのだと、意味を取り違えられたのだとわかったけれども、押し寄せる快感にすぐにくらまされてしまった。明確な意思をもって前と後ろのいいところばかりを集中して責められたら、そう長い間保ちこたえていられるわけがなかった。
「ぃ……やだ、も…………」
「もっと? 恭弥……もっと欲しいなら、呼んで、もっと」
「ちが、あ、あぁ、──あ……っ」
こらえきれなくなって、声が意味のある音では続かなくなって、他人のもののようなうつろな泣き声がついに止まらなくなった。吸いつきながらつながる部分から広がる甘い疼きは急カーブを描いてほどなく頂点に達し、大きな手のひらに包まれたヒバリはすでに張り裂けそうに痛んでいる。
ふわりと、頭の奥のほうがゆるくなる感じがした。気が遠くなりかけていた。恭弥、とやわらかく呼ばれて、ヒバリは夢中で声のするほうを探した。目が合うと安心して、また大きな声を出してしまった。
「ダメならもう、いって……オレはいいから、我慢すんなよ」
「っ、や、……だ……っ」
「強がるなって。つらそうだ」
ちがう。快楽は欲しい。
いきたい、いかせてほしいと口に出してねだることも平気だ。
ただ──真昼のあかるさの残る部屋でこのまま意識を飛ばして、終わりを迎えてずるずると眠ってしまうのはいやだった。
たとえ我を忘れていても意識があかるいうちはディーノに届く。ひとりで夢の中に追いやられる時間が惜しい。ディーノは何もわかっていない。
ヒバリは自分の指を口に入れて強く噛みしめた。
「痛、…………っ」
つぷりと皮膚に食い込むまで歯を立てると、ぼやけていた意識が少し戻ってきた。
「なにすんだバカっ、恭弥っ」
ディーノがヒバリの手を口から引きはがした。咬んだ部分が小さな傷になっている。皮膚の下に少し血が滲んでいたけれど不思議と痛くはなかった。
「……ほら見ろ。血が出ちまったじゃねーか」
「平気だよ。こんな傷、たいしたことない」
「恭弥」
こわい声で叱られたけれどもやめない。
「また血が出たら、あなたがなめてくれればいい。なめるの得意だよね」
「おまえなあ」
「──続けて」
咎めるような目でヒバリを睨んでいたディーノが、諦めたのかふたたび動き出した。
なんて強情なヤツだと思っているのに決まっている。両手の自由を奪われたのは「咬むのはだめ」という意味の、わかりやすい見せしめ。これくらいでおとなしく言うことを聞くと思われているのは意外だった。そして少しうれしかった。
眠るのは、もう少し日が陰ってから。部屋を照らすあかるい光が消え失せて、ディーノの姿がはっきり見えなくなってからでいい。
だからヒバリは何度でも、いつまでも、あきらめ悪く最後まであがいてみる。
傾きかけた陽の下で。
あかるい部屋で。エロ習作。でもえろくない……。
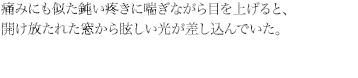
 読む
読む